「SNSを仕事にしよう!」♯5
書く仕事で生きていくためには?

副業・転職を目指す人がクリエイティブスキルを求めて集まるデジタルハリウッドSTUDIO横浜。
1月27日、「SNSを仕事にしよう!」を合言葉にオンラインセミナーが開催されました。
第5回のテーマは
「書く仕事は、文章力“以外”が8割」。
ライター、コラムニストとして活躍し、昨年『書く仕事がしたい』(CCCメディアハウス)を上梓された佐藤友美(さとゆみ)さんをお迎えして、パラレルキャリア研究所代表の慶野英里名さんと、赤裸々なトークが展開されました。
「書く仕事の魅力」から「SNSを活用してキャリアを切り開く秘訣」まで、“書く”を仕事にするためのヒントをレポートします。
特に、「ライター」にも「SNS担当者」にも共通して大切な「相場感」については、役に立ったという声が多く挙がりました。
さとゆみさんが実践した、SNS経由で仕事を獲得したエピソードも詳細に解説するなど、「SNSで書く仕事をする」ためのヒントが満載の90分となりました。
書く仕事の魅力は、新しい発見があること

慶野:私は『パラレルキャリア研究所』という団体を運営しており、複数の仕事を持つ新しい働き方「パラレルキャリア」について、講演や執筆を行っています。
ただそれは副業で、本業は出版社の編集者。
元々は、新卒入社で編集者を志望したのですが、庶務に配属されたことをきっかけに、社外で文筆業を目指して『上阪徹のブックライター塾』へ入塾。そこで同期としてさとゆみさんと出会いました。
さとゆみ:私はテレビ制作会社でADをしていたんですが、結婚をきっかけに退職し、「書く仕事がしたい」と思い、出版社に勤める友人に相談。
彼女がファッション誌の仕事を紹介してくれて、ライターとしてのキャリアが始まりました。
同時に、売れっ子だったライターさんのアシスタントにもなり、ヘアスタイルや美容を中心に仕事を増やしていった感じです。
慶野:そこから新たな価値を見出すために『ブックライター塾』へ通われたんですか?
さとゆみ:当時ファッション誌には「ライター40代定年説」があって、「70代になっても書ける仕事はなんだろう」と思った時に上阪徹さんの
『職業、ブックライター。』という著書に出会ったんです。
その本を読んで、書籍なら年齢を重ねても書いていけるかも…と考えて入塾しました。
そこから書籍の仕事をいただくようになり、現在は自著やエッセイ、コラム、企業のSNSなども書いています。
慶野:かなり多彩に仕事をされていますが、さとゆみさんにとって、書く仕事の魅力ってなんでしょう?
さとゆみ:最初はとにかく取材が好きでした。
芸能人や知識人の方の話を近い距離で聞けて、質問もできるなんて、すごく魅力的な仕事だなと思って。
たとえ興味の無かったことでも、世界が広がるし、勉強になります。
ただ最近は、自分の考えていることを書くことも楽しいなと。
どちらにしても、書く時って必ず新しい発見があるんです。
インタビュー中や、頭で考えているだけでは気づかなかったことを、書くことで発見できる。
自分を取り巻く世界に深くタッチできる感じがとても面白いですね。
慶野:書く仕事には、書く以外の魅力もあるということですね。
そして書く仕事には、書く以外の作業も結構あるんですね?
さとゆみ:仕事の9割は「書いていない」時間だと思います。
ヘアスタイルの記事を例にしても、まず読者の髪の悩みをリサーチして、美容師さんからトレンドを聞いて、企画を考えて、通ったら誰に取材するかを決めて、アポイントをとって。
打ち合わせに行って、モデルさんを決めて、撮影して、写真を選んで…。
となると、原稿を書くのは最後の1割です。
一番重要なのは、“相場感”
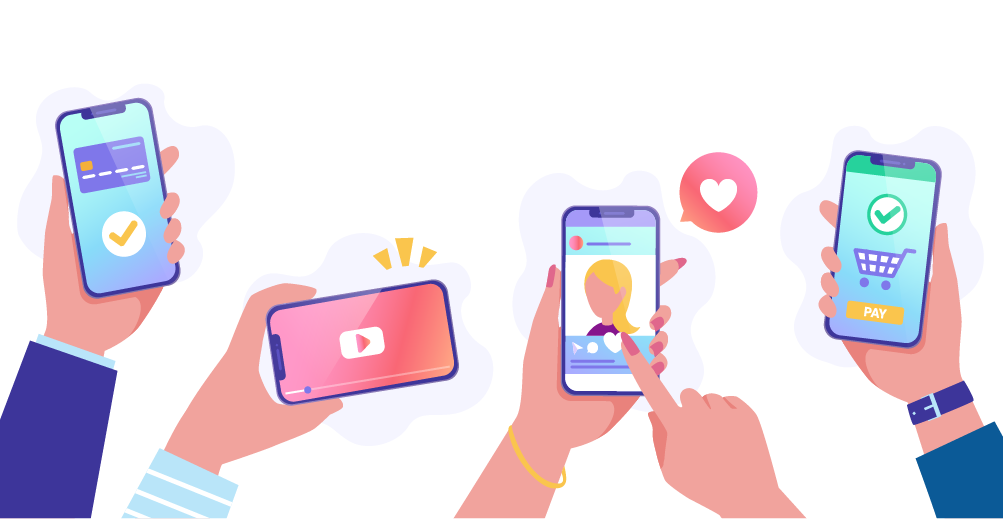
たしかに、さとゆみさんの著書『書く仕事がしたい』の帯には、「書いて生きるには、文章力“以外”が8割」と書かれており、それが今回のイベントタイトルにもなっています。
さとゆみさんは書く以外に、どんなスキルを磨きながら仕事をされているのでしょう。
さとゆみ:私が一番大切にしているのは“相場感”です。
“相場感”というのは、文章を届けたい相手が、「この情報を聞いて驚くか」「常識だと思うか」「このブランドは安いと感じるか、日常使いと感じるか」など、読者がどんな人たちかを考えることです。
慶野:“相場感”は、書籍やWEB、SNSの文章にも必要なものですか?
さとゆみ:すべてに。
書く仕事をされたいと思った方は、たぶん出版社やWEB媒体に「原稿を読んでください」と言うよりも、“相場感”を考えて企画を出した方が仕事は取りやすいです。
例えばWEB媒体に向けた企画だったら、「巷で話題のこういうことを記事にしたら、きっと読まれると思います。その取材ができます」とか。
“相場感”を養うためには、読者層についてきちんと調べたり、ヒアリングしたりして、読者にとってどの情報が新しいのか遅いのか、その感覚を持つことが大事です。
ですから”相場感”の観点から言うと、社会人経験がある人や、別の業界で働いた経験がある人は、有利な点も多いんですよ。
慶野:励まされますね!
SNSの仕事では、“相場感”はどのように活かされていますか?
さとゆみ:企業のSNSでは「自分達が語りたいこと」というより、「自分達が持っている商品やサービスは、こんなシーンでみなさんのお役に立てます」というふうに書かせていただくことが多いですね。
一方、個人のSNSやブログで書く書評は本の内容というよりも、読んで思い出したこと、考えたことをできるだけ書いています。
それは何故かというと、個人的なエピソードは全く同じ経験をしていなくても、共感につながることが多いから。
しかもSNSって、個人と個人がつながるところじゃないですか。だから自分の想いを、なるべく噓なく書くようにしています。
慶野:確かにSNSは、シェアやコメントができて、ユーザーとの距離が近いことが特徴です。
だからこそ、“相場感”を間違えると的外れな内容になって、ファンが去ったり、様々な齟齬も生まれてしまうそこは気をつけないといけないですよね。
さとゆみ:TwitterやInstagramって、「世の中に向かってつぶやいている」と思っているかもしれませんが、結局誰かに向かって話しているんですよね。
だから、伝えたい人の顔を思い浮かべながら書くと、伝わりやすいかもしれません。
広大なSNSでどうやって見つけてもらうのか?

SNSでは、自分が誰に伝えたいか、届いて欲しいかが大切だというさとゆみさん。
noteの発信を通じて出版社からオファーを獲得した際の秘訣も教えて下さいました。
さとゆみ:例えば自分のプロモーションとしてnoteを書いているのであれば、まず相手が「どういうnoteを見ているか」「どういう記事なら仕事を頼みたいと思うか」という目線で書いた方がいいと思います。
誰に届けるかを具体的にイメージして。私は「書籍のライターになりたい」と思ったときに、意識的にnoteを使い始めました。
まず、書籍の編集者さんにみつけてもらうにはどうすればいいだろうと考えたのですが、編集者さんは、担当した本の感想は必ず読んでいるだろうなと思ったんです。
それで、お仕事したい編集者さんが担当した書籍の書評を100日続けたら、仕事につながったこともあります。
慶野:そういう使い方は、SNSで夢を叶えたいと思っている方にとって、今のお話は非常に参考になります。
さとゆみ:もう一つやっていたのが、「書籍にあることを実践したら本当に人生が良くなるのか?」を検証するnoteです。
『フランス人は10着しか服を持たない』という書籍を元に、本当に10着で何か月過ごせるかを検証したりしていました。
そこまでやると、必ず編集者さんに届きます。
慶野:ブランディングやプロモーションのためにSNSをされて、素敵な写真を撮ったり、仕事の発信をされている方は多いと思います。
でも、スカウトされたい人の心にどうすれば食い込めるか、このレベルまで考えて継続したら絶対チャンスはありますよね。
さとゆみ:この間講談社のWEBマガジン
『mi-mollet』の副編集長の方に、「ライターさんから売り込みがあったらどういうところを見ますか」とお聞きしたんですが、その方は必ずInstagramを見に行きます、とおっしゃっていました。
センスとか興味、写真の撮り方、そういうところを必ず見に行くと。
ですから、出版社に売り込みに行った際にはSNSが必ず見られると思って、日頃から運用していくといいと思います。仕事とプライベートのSNSは分けていいので。
慶野:確かに、仕事用のアカウントは持った方がいいと思います。
どの仕事相手、自分がいつか仕事したい方にも見られて恥ずかしくない、かつ戦略的にこれをやりたい、ここまでやっていると発信するSNSをやればいいんですよね。
ちなみに、ここデジハリ橫浜にもSNSを学べるSNS運用マネジャーやSNSクリエイターコースがあり、学びたい人も増えていますね。
人間性は文章ににじみ出る。
性格の推敲を

ここまでは、SNSの攻めのプロモーション、ブランディングについての内容でした。
次に話題になったのは守り。ネガティブな自分を見せない大切さについて、お話が続きます。
慶野:クライアントの愚痴をSNSに書いてしまうフリーランスの方もいますが、私はその人には絶対にお仕事を紹介しません。
紹介したクライアントの愚痴を書かれてしまう可能性が怖いので。
さとゆみ:私も『書く仕事がしたい』を書くときに、編集者さん20人ぐらいに聞いたんです。
どんなライターと仕事がしたいか、どんなライターが嫌か。
嫌のほうの答えのほとんどは「SNSで仕事相手の悪口(or仕事の愚痴)を書く人」でした。
何か困ったことがあるなら、直接言ってほしいし、話してくれれば絶対改善しようと思う。
でも、先にSNSで書かれると、そもそもその人にコミュニケーション能力が無いように見えると。
すごくネガティブキャンペーンだよねって。
慶野:SNSは、自分のいいところも悪いところも垂れ流す可能性があるので、やっぱり戦略的に使う必要がありますよね。
さとゆみ:『女の運命は髪で変わる』という本を書いた時に、編集長に、「売れる著者になりたかったら、とにかく性格を良くして下さい」と言われたんです。
性格が良くないとみんなに応援されないから。私、それまで結構性格が悪くて(笑)。
売れっ子のライターさんがいたら、早く妊娠して産休にならないかなあとか、
ご主人転勤で海外に行ったりしないかなあ。そうしたら私、その仕事できるのに、とか。
でも編集長に指摘されてから、とにかく性格のいい人になろうと思ったんです。
飲み会に行っても靴を揃えるようになったりとか(笑)。この仕事って、裏表を使い分けられるほど器用にできる仕事じゃないんです。
文章には人間性が全部出る。だから実際に人間性を整えた方が、良い人に見せるよりも手っ取り早いと思います。
慶野:明確には書いていなくても無意識の偏見がにじみ出ると、ファンが離れちゃうんですよね。
編集者さんがついた仕事だと直してもらえるかも知れないけど、SNSだとダイレクトに届いてしまうかも知れません。
だから一回推敲して欲しいし、性格も推敲した方がいいかも…!
さとゆみ:性格も推敲!(笑)。
でも、たしかに人格は文章に出ますよね。
例えば私が慶野さんのことを取材して、慶野さんのことを書くとします。
たとえ、自分のコメントを一切入れなかったとしても、どうやったって書き手の私はただの黒子にはなれない。
素敵だと思ったこと、心に響いたところを書けば、「私が慶野さんをどう紹介したいと思ったか」がにじみ出ちゃうんです。
だから色々な経験をした方がいいし、いろんな感情を知っていると書き方にも深みが出るから、辛い経験も肥やしになります。
書く仕事をしている限り、どんなに嫌なことがあってもそれは文章に生かすことができるし、回収できるんです。
まずはSNSを始めよう
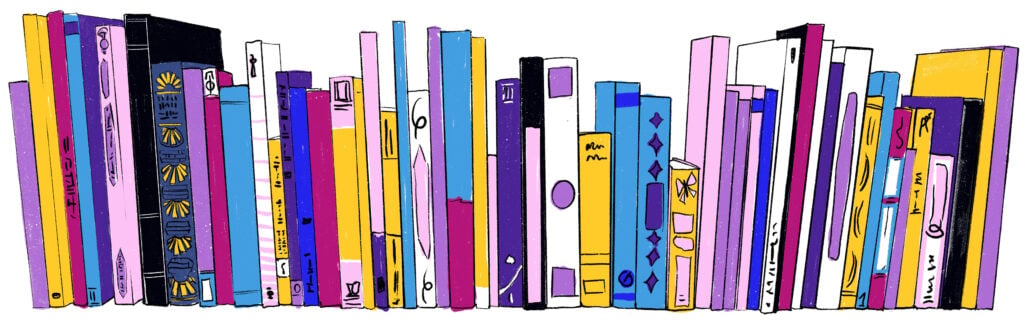
イベントの最後は、『書く仕事がしたい』の担当編集者 CCCメディアハウスの田中里枝さんがサプライズゲストとして登壇。
3人で、参加者の背中を押してくれました。
田中:私はどんな文章も手紙だと思っています。本だったら読者、SNSも、顔の見えない誰かに届く手紙だと。
ラブレターってめっちゃ相手のことを考えて書くじゃないですか。
受け取った相手がどう思うんかなとか、うまいこと気持ちが伝わるかなとか。
文章を書くとき、読む相手への思いやりや愛があれば、その文章は読む人の心を打つんと違うかな、と。
慶野:SNSはチャンスがあるからみんな本当に始めて欲しいです。
ご興味があれば、登壇者のSNSもフォローしてみてくださいね。
(※下記にプロフィールがあります)
さとゆみ:『書く仕事がしたい』は、書きたいみなさんのお役に立てる本になっていると思うので、ぜひ読んでいただきたいです。
そして、このデジタルハリウッドSTUDIO横浜さんのような学びも場へもぜひ!
慶野:人が集う場所ってめちゃくちゃ大事です。同じ興味関心、志を持った人と一緒に成長していく、そこからチャンスを分かちあうことが沢山ありますよ!
クリエイターは表現がお仕事。
今回のイベントは、「書く仕事」で生きる、生きたいと思う方にとって、一歩を踏み出すきっかけになったのではないでしょうか。
参加者は200人を越えており、講座後には、質疑応答の時間も。
「文章を書くテクニカルなコツは?」「地方で東京の書く仕事を獲得するには?」など大盛況で幕を閉じました。
デジタルハリウッドSTUDIO横浜では、今後も「SNSを仕事にしよう!」をテーマに、新しい働き方の講座を開催予定しています。
【登壇者プロフィール】

佐藤友美(さとゆみ)
976年北海道知床半島生まれ。
テレビ制作会社のADを経て文筆業に転向。
元東京富士大学客員准教授。書籍ライターとして、
ビジネス書、実用書、教育書等のライティングを担当する一方、独自の切り口で、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆している。近著は、『書く仕事がしたい』(CCCメディアハウス)、8万部を突破した『女の運命は髪で変わる』(サンマーク出版)など。
【公式サイト】https://satoyumi.com/
【書く仕事がしたい】http://books.cccmh.co.jp/list/detail/2350/
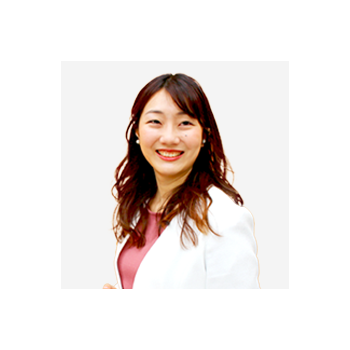
慶野英里名(けいのえりな)
パラレルキャリア研究所代表/一般社団法人クロスオーバーキャリア理事長。
都内の出版社にフルタイムで勤務しながら、2018年に「パラレルキャリア研究所」を設立し、「パラキャリ酒場」「秘境PR部」など、複数の軸足を持つ働き方・パラレルキャリアに関するイベントを80回以上開催。
イベントの広報はSNSを活用して実施しており、企業・自治体向けにSNS活用のアドバイザー業務なども行う。
【Facebook】https://www.facebook.com/ erina.takamura.5
田中里枝(たなかりえ)
CCCメディアハウス編集者。担当した書籍が次々話題となり注目を集めている。
担当書籍は、『書く仕事がしたい』佐藤友美著(現在3刷)のほか、1月末に発売した新刊『ストーリーで語る』秋山楓果(あっきゃん)著、『三行で撃つ』近藤康太郎著(5刷)、『兄の終い』村井理子著(8刷) 他多数。
【Twitter】https://twitter.com/lilico_i
構成/笹間 聖子
ライター、時々編集者。書籍・雑誌・WEB・PRツールに携わる。進行中のジャンルは、幼児教育/オモチャ/生活/医療/ホテル/グルメ/コスメ。ブックライター塾7期生。(Twitter)https://twitter.com/if9o7STm9Ekpyc8
デジタルハリウッドSTUDIO横浜では、「SNSを仕事にしよう!」を合言葉に今後もオンラインイベントを開催していきます。
【オンラインイベント情報】
https://school.dhw.co.jp/school/yokohama/event/20191231.html

